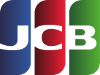過去に発表されたクレジットカードや電子マネーに関する統計データやアンケート調査は、日が立つにつれてどんどん使えなくなっていくもの。
しかし、○年時点での情報を調べたい方にとっては有益なデータとなる場合もあるかと思うので、過去、当サイト『クレジットカードの読みもの』上で紹介したことがあるデータやアンケート調査結果は削除せず、1記事にまとめてみることにしました。
キャッシュレス決済に対する日本人の価値観にはどう変化があったのか、気になる方は参考にどうぞ(ページ下部にいくほど古いデータになる&記述は記録としての価値をもたせるためにも公開当時のまま)。
- 2020年の統計データ:
- 2019年の統計データ:
- 2018年の統計データ:
- 2017年の統計データ:
- 2016年の統計データ:
- 2015年の統計データ:
- 2014年の統計データ:
- 2012年の統計データ:
- 他の統計データまとめ:
- 統計データを見つけ次第、まとめます:
2020年の統計データ:
2020年に集計された統計データやアンケート調査結果です。
三井住友カードがパルテノン神殿をやめたことに対する賛否:
三井住友カードといえばパルテノン神殿…というくらいに浸透していた券面デザインが、ガラリと変更されたことに対するアンケート調査結果です。

新デザインと旧デザインのどちらが良いか、Twitterのアンケート機能を利用して取得したものがこちらです(当該ツイートはこちら)。
質問です。
三井住友カードの券面デザインが新しくなりますが、新しいデザインと古いデザイン、どちらが好きですか?
教えて下さい。
総計847名の方に協力をいただいたアンケート結果は下記の通り。

ご覧いただいたように全体の58.5%の方が新デザインを肯定的に捉えているという結果になりました。
- 全体の58.5%:肯定的な意見
- 全体の41.5%:否定的な意見
反面、全体の41.5%の方が否定的な感想を持っていることを考えると、現時点で三井住友カードを保有している方の中にも不満を感じている方が多そうな感じです。
パルテノン神殿の廃止に不満な人も:
実際、パルテノン神殿が描かれた旧デザインへの愛着を感じてる人は多いみたいで、今回のデザイン変更について『パルテノン神殿が倒壊した!』とか、『新デザインはパルテノン神殿を壊す時に踏んでしまった鏡みたい』といった意見なんかも。
たしかに三井住友カードといえばパルテノン神殿という方も多いと思うので、それだけに今回のデザイン変更は衝撃でしたね(印象的なツイートを引用)。
敢えて他社のカードを例に出しますが、もしアメックスが未来を考えてカードデザインから百人隊長を無くすと発表すれば悲しむ人が多くいると思います。
それだけ代名詞だということ。
三井住友カードの代名詞といえばやはりパルテノン神殿ではないでしょうか?
中でも三井住友カード プラチナの券面デザインについては、旧デザインのほうが圧倒的に格好いいと思う私。

せめてプラチナカードにだけはパルテノン神殿を残せなかったものかと思うばかりです(三井住友カード プラチナの公式ページはこちら)。
主要ポイント制度のどれが一番人気か2020年版:
楽天ポイント、Tポイント、Ponta、dポイントの主要4大ポイント制度はどれが人気なのかを調べてみた結果です(2020年7月24日実施の調査結果はこちら)。
質問です。
ファミリーマートやローソンが下記4つのポイントサービスに対応したとします。
- Tポイント
- 楽天ポイント
- Ponta
- dポイント
この際、1つしか貯めることが出来ない&すべて同じポイント還元率だとしたら、あなたはどのポイントを優先して貯めますか?
教えてください。
早速、気になる統計結果を円グラフにまとめるとこんな感じ。
- 楽天ポイント:59.9%
- dポイント:18.4%
- Tポイント:14.4%
- Ponta:7.3%

ご覧のように楽天ポイントを選ぶ人が圧倒的に多く、全体の6割が楽天カード派という形となりました。
うーん、すごい比率ですよね、これ。
かつての王者であるTポイントの奈落:
反面、かつての絶対王者だったTポイントへの支持は、全体の14.4%と寂しい限り。
たぶんですが2015年頃に同様のアンケートを実施していたらTポイント派が6割で、残りをPontaと楽天ポイントが取り合うような形になったと思うだけに、時代の変化とはすごく残酷なのだなぁ…と思わされますね。
下記のように2019年時点の調査結果と並べてみると、Tポイントへの支持率低下がよくわかるのではないでしょうか?
- 2019年2月時点:Tポイント派は19.3%
- 2020年7月時点:Tポイント派は14.4%

見事なまでにdポイントにひっくり返されてしまった形となります。
Ponta支持が伸びない:
ついでにもうひとつ気になるのが、事実上のauグループ入りをしたPontaへの支持率がじわりと低下している点(引用元はこちら)。
KDDIは2020年5月21日以降、ポイントサービスをau WALLET ポイントからロイヤリティ マーケティング (以下 LM) が運営する共通ポイントサービス「Pontaポイント」へ変更します。
これにより、さまざまな提携社での商品購入やサービスのご利用でたまる「Pontaポイント」が、スマホ決済サービス「au PAY」や「au PAY カード」の決済ご利用分とダブルでたまるようになるほか、「au PAY アプリ」ひとつでカード提示によるポイント獲得から決済までが可能になります。
今回のアンケート調査は2020年7月24日付けでのものなので、そろそろこの影響を折り込んだ結果になっていてもおかしくなさそうなんですが、結果は2019年よりも支持を落とす形となりました。
つまりau携帯の利用者でもPontaを優先して貯めている方はまだまだ少ない。そう捉えられる結果になったと言えそうです。
2019年の統計データ:
2019年に集計された統計データやアンケート調査結果です。
現金を汚いものと考えている比率:
クレジットカードや電子マネーを使う目的は人それぞれ…ですが、その中には一定数、『誰が触ったかわからないフケツな現金を触りたくないから』という理由でキャッシュレス決済を好んで使う方たちがいます。
事実、先日も社会学者の古市憲寿氏がテレビで『現金て汚いじゃないですか!』と発言したことが話題になったばかり(引用はこちら)。
古市氏は「そもそも、現金って気持ち悪い」などと持論を展開。
「誰が使ったかわからない。現金て汚いじゃないですか。汚いものにできるだけ触れたくないので、できるだけ電子マネーで払うようにしています」などと述べ、普段電子マネーで支払いをしていることを明かした。
ただ、どのくらいの方が紙幣や硬貨を汚いものとして認識しているのかがわからなかったので、今回は参考までにレストランの店員が素手でお金を触るのは汚いと思うかどうかについて5,028名の方に質問を投げかけてみました。
全体の60%は抵抗を感じない:
気になるその結果は…というと、現金を汚いものとして捉えている日本人はまだまだ少数派な様子(統計結果はこちら)。
飲食店の店員が、素手で小銭や紙幣を触ってるのを見て、不潔だと感じますか?
- 15%:かなり不潔に感じる
- 25%:少し抵抗を感じる
- 60%:抵抗を感じない
「かなり不潔に感じる」と「少し抵抗を感じる」を足しても40%程度…と、日本人はそれほど現金を不潔と感じてないことがわかります。

意外といえば意外な結果ですよね、これ。
全体の40%は抵抗を感じている:
但し、全体から考えると少数派とはいえ、約40%もの方が現金を不潔なものとして感じていることもまた事実。
たとえば今回のTwitter統計に対して寄せられた意見の中に下記のようなものがありましたが、これをされた場合には潔癖症ではない私でもちょっと嫌な気分になりますね(こちらより引用)。
現金オンリー前払いの店でソフトクリームを頼んだら、お金触った後そのままコーンを握ってたのは嫌だったなぁ…
ソフトクリームの上のほうだけを食べて、捨てちゃうかもです。
強く抵抗を感じる層も少なくない:
他にも『手洗いをせずにそのまま仕事してる店員さん見たら、もうそのお店に行きたくない…』という、強めの拒否感がにじむツイートも存在(こちらを参照)。
レジした後に、手洗いせずにそのまま仕事してる店員さん見たら、もうそのお店に行きたくないな。。
こちらの方を含め、今回の統計で「かなり不潔に感じる」を選択した約15%の方はちょっとした不潔行為も不快に感じてしまう可能性が高いため、飲食店の方は『そんなのほんの少しの人間だけだろ?』と思わず、くれぐれも注意してください。
レジを担当したら即、手洗い&消毒あるのみです。
キャッシュレス消費者還元事業が成功するかどうか:
2019年10月に開始された日本政府による「キャッシュレス消費者還元事業」(引用元はすでに閉鎖済み)。
キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9カ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。
この還元事業が成功するかどうかをTwitter上でアンケート調査した結果が下記のものとなります(当該ツイートはこちら)。
- 大成功する(一気に浸透する):3%
- 広く浸透するが大成功までは行かない:16%
- 少しは浸透するが影響は小さい:57%
- まったく成功しないと思う:24%

ご覧のように合計1,302名の方に回答をいただきましたが、そのうち、81%もの方がキャッシュレス消費者還元事業の効果を懐疑的。
いくら5%分のキャッシュバックがあるといっても、これだけでクレジットカードやスマホ決済が普及するとはみなさん考えていないようです。
キャンペーンが無くてもPayPayを使い続けるかどうか:
PayPayでは2回目の100億円あげちゃうキャンペーンが5月中旬に終了し、のべ200億円ものキャンペーン予算を消化されたわけですが、ここで疑問なのは、200億円をバラ撒いたことによってPayPayが普及したのかどうか。
そこで今回は恒例のTwitterアンケートを利用し、キャンペーンが終了してもPayPayを利用しつづけるかどうかを調査してみた結果が下記の通りです。
- 11%:引き続き継続的に利用する
- 44%:キャンペーン次第で利用する
- 20%:あまり使う予定はない
- 25%:そもそもPayPayを使ってない
PayPayを利用したことがある方に質問です。
第2段の100億円あげちゃうキャンペーンが終了しましたが、引き続き、キャンペーンが終わった後もPayPayを利用しますか?教えてください。
このうち25%の方はそもそもPayPayを利用していない方なので除外し、再調整してみた比率はこのような数値となります。

大多数の人はキャンペーン次第:
ご覧いただければ分かる通り、全体の58.7%もの方がPayPayをキャンペーン次第で利用すると回答。
そして26.7%の方はキャンペーンが実施されてもPayPayを使う予定がないことを踏まえると、PayPayを今後も継続利用しようと思っている人はわずか14.6%のみであることがわかります。
- 14.6%:引き続き継続的に利用する
- 58.7%:キャンペーン次第で利用する
- 26.7%:あまり使う予定はない
うーん、これじゃ200億円をバラ撒いた効果があったとは、なかなか言えない状況があるのではないでしょうか?
そういう私も、次の魅力的なキャンペーンが開始されるまではPayPayを利用する予定はありません。
他社の統計データでも類似な結果に:
また、ジャストシステムが2019年4月に実施した類似の統計調査でも、下記のように同様な結果に(設問の対象となる324人からの回答)。

約4割が、大型キャンページ時のみ、「QRコード決済」「バーコード決済」を利用
QRコード決済やバーコード決済の利用経験者のうち、「日常的に利用している」人は34.6%、ポイント還元といった「大型キャンペーン時以外は利用しない」人は44.2%、「キャンペーンに関わらず、頻繁には利用しない」人は16.7%でした。
こちらはPayPayのみに限った話ではなく、楽天ペイやLINE Payといった他のQRコード決済全般の話になるため、継続的に利用すると回答した方も36.2%ほど存在。
しかし、それでもキャンペーン次第で利用率が変化する傾向には変わりがないと言えそうです。みなさんほんと、お得じゃないとQRコード決済を使いません。
クレカ対象だと異なる結果に:
ちなみに。
『そんなことを言ったらクレジットカードだって、ポイントが貰えなくなったら誰も使わないんじゃないの?』と思われる方もいるかもしれませんが、クレジットカードの場合には異なる調査結果になるのが面白いところ(調査結果はこちら)。
クレジットカードで支払いをするともらえるポイント。
このポイント制度が将来的に廃止されてしまったとしても、あなたはカードを利用し続けますか?(100万円の支払いをしてもポイント獲得が0円になるということ)
結果は61%の方がポイントが貰えなくても継続利用すると回答しました。

クレカにはポイント以外にも強みがある:
これはまぁ、クレジットカードはネット通販等の支払いに便利とか資金繰り面での強み、そして家計簿ソフト等との親和性の高さがあるからと推測。
- 支払いが後払いになること
- 利用履歴がデータ化されること
- 通販等で便利であること
- 電子マネーとヒモ付けしやすいこと
- 現金を持ち歩く必要性がないこと
もちろん電子マネーやQRコード決済でお得なキャンペーンが実施されている場合にはそちらに流れてしまう可能性は高いですが、少なくともクレジットカードはひとつの支払手段として広く受け入れられてるのは間違いなさそうです。
言い換えるなら、クレジットカードはすでにインフラである…とも言えますね(カード払いのメリットは下記記事も参考に)。
主要ポイント制度のどれが一番人気か:
Twitterのアンケート機能を使って『将来、ローソンやファミマで、Tポイント、楽天ペイ、dポイント、Pontaの4つが貯められるようになったとしたら、みなさんはどのポイントを選びますか?』という質問をぶつけてみました。
将来、ファミマやローソン等のコンビニで下記4つのポイントが貯まるようになった場合、みなさんはどのポイントを優先して貯めますか?
1つだけお選びください(還元率やキャンペーン等の条件はすべて一緒とする)。
- Tポイント
- 楽天ポイント
- Ponta
- dポイント
理由は単純。
この質問でどのポイント制度が選ばれるかを見れば、今、多くの消費者がどのポイントプログラムに一番魅力を感じているかがわかるためです。
結果は楽天ポイントの圧勝:
気になるその結果は…というと、下記のように楽天ポイントの圧勝という結果に(2,375人によるアンケート結果)。

個人的には楽天ポイントには勝てないまでもTポイントには優位性があると思っていたのですが、これほどまでに楽天ポイントとの格差があるとは思いませんでした(楽天ポイント50%、Tポイント40%、残り10%くらいだと思っていた)。
- 私の予想:楽天ポイントとTポイントは僅差
- 実情:楽天ポイントによる圧勝
また、Tポイントとdポイントの差がわずかなことも注目すべき点。このままだと近いうちに、dポイントに追い抜かれてしまうこともありえる話でしょう。
PayPayの100億円あげちゃうキャンペーンを利用するかどうか:
PayPayの第2回100億円あげちゃうキャンペーン積極的なのはを利用するかどうかを調査してみた結果です(アンケート結果はこちら)。
- 10.2%:上限限界まで使う予定
- 45.9%:使えたら使うかな…という程度
- 43.9%:使う予定なし(興味ない)
この結果は私のアカウント「クレジットカードの読みもの」という、クレジットカード等のキャッシュレス決済に興味がある方が主な回答者なのにも関わらず、半数近くの方がまったく利用する予定がないと回答したはちょっとした驚きでした。

ご覧のようにキャンペーンを積極的に使おうとする人と、キャンペーンにまったく興味がない人が真っ二つに分かれてる、そんな感じです。
5年後、スマホ決済はどこが主流になるか?:
5年後のスマホ決済はどこの業者が勝ち抜いているのかを予想してもらった回答結果です(2019年3月時点での調査結果)。
- 16%:PayPay
- 31%:LINE Pay
- 20%:その他(楽天ペイやd払いなど)
- 33%:キャンペーンが終わればどれも衰退

かろうじてLINE Payに期待している方が多い印象は受けますが、それ以上にキャンペーンが終わってしまえばスマホ決済を使わない…という回答が多かったのは予想通りというかなんというか。
その上で寄せられた下記ツイートの意見には私も納得でした。
一旦衰退しそうだが、最終的になんだかんだギリ2%とか薄利でもやっていける体力のある企業と使える店の普及度とポイントとカード残高の融通度合いで決まりかな。
— ハカセ (@sakanahakase) March 16, 2019
その点、LINE Payと楽天系列(ポイント、カード、Edy、ペイ)がリードの印象。PayPayは囲い込み型なのでキャンペーン終わるとキツイ。 https://t.co/m7Go9zDVeQ
残るとしたらLINE普及率の高いLINE Payか、楽天経済圏が強い楽天ペイだけで、キャンペーンで囲い込みをしているだけのPayPayはちょっと厳しめですね。
なにか他のメリットでも出来ない限りは、使う理由がありません。
2018年の統計データ:

2018年に集計された統計データやアンケート調査です。
若年層の電子マネー保有率について:
10代や20代といった若年層が、SuicaやWAONといった電子マネーについてどう思っているのかを調査した統計調査です。
若年層リサーチ結果を発信する「TesTee Lab!」にて、10代、20代の若年層男女1,194名(10代566名、20代628名)を対象に電子マネーに関する調査を実施しました。
- 調査期間 :2018年7月15日(日)
- 調査対象 :10代、20代 / 男女 / 自社モニター会員 / Android、iPhoneユーザー
- 割付方法 :1,194サンプル(10代566サンプル、20代628サンプル)
まず、若年層の電子マネー保有率は下記の通り。
- 10代の保有率:44.2%
- 20代の保有率:60.7%

ご覧のように電子マネー保有率は20代でも約6割で、10代に至っては半数以下の保有率という結果に。
これは逆に考えると、約4割の20代は電子マネーを持たずに生活をしていることでもあるので、これじゃお世辞にも電子マネーが普及しているとは言い切れない状況があるように思います。
保有中の電子マネーは交通系ICカードが大半:
では、どのような電子マネーを10代、20代の若者は保有しているのか、その統計結果がこちら。

20代ともなるとnanacoやWAONの保有率が若干あがりますが、電子マネーを保有している若者の大半が交通系。
つまりSuicaやPASMO、ICOCAといった交通系ICカードのみを保有していることを考えると、まぁみなさん、支払い向けというよりかは通学や通勤のために電子マネーを持ち歩いている可能性のほうが高そうな感じです。
- 間違い:支払いのために電子マネー保有
- 正解:通学や通勤のために電子マネー保有
こういったところからも、若年層に電子マネーが普及しているとは言い難い状況がありますよね。
現金払いと電子マネー払いの比重:
更にそれを裏付ける統計結果がこちら。

10代はともかく20代でも電子マネーの利用頻度は低いようで、実に全体の78.9%が電子マネーよりも現金払いをよく利用すると回答。
- 10代の現金派:87.4%
- 20代の現金派:78.9%
電子マネーを普段使いしているキャッシュレス派は、きわめて少数派であることがわかります。
約4割の若者はキャッシュレス社会を求めていない:
それじゃ若年層が現状を変え、キャッシュレス社会を求めているのかといえばこちらも微妙みたいで、約4割の方がこれ以上の電子マネー普及に否定的な統計データも。

まぁ確かに現金払いのままでも不自由しない状況があるわけですからその気持ちもわからないでもないんですが、それでも、これだけ多くの10代、20代が電子マネー普及に対して否定的というのはちょっと残念だなぁ…と思います(しかも10代より20代のほうがキャッシュレス化に否定的)。
クレジットカードの利用率も低い若年層:
加えてこの電子マネー利用に関する統計データには、他の支払い手段に関する統計結果も存在。
こちらを見ると電子マネーよりもクレジットカードのほうが日常利用されていることがわかりますが、それでも全体からすると41.7%(20代の場合)と過半数以下。

いかに日本国内の支払い手段が現金決済に偏っているかがわかる結果となりました。
デビットカードやスマホ決済も少ない:
また、現時点で普及が期待されているQRコード決済も利用率はまだまだ。
同様に10代でも持てるはずのデビットカードも利用率は低め…と、現金払い以外の支払手段についてはどれも似たり寄ったりな結果になってしまってるのは、若年層がキャッシュレス決済に対して魅力を感じていない何よりの証拠なのかもですね。
このままだと2020年になっても、たとえ2030年になっても日本の決済手段は変わっていかないので、今のうちから若年層にも魅力を感じてもらえるようなメリットを、私たちクレジットカード業界の人間や、日本政府は提供していかないといけないのかなと思います(なぜキャッシュレス決済が普及しないといけないのかは下記記事参照)。
2017年の統計データ:

2017年に集計された統計データやアンケート調査です。
年収が高い人ほどクレカを使い分けている:
市場調査を専門にしているイプソス株式会社というところが、大規模なクレジットカード利用実態調査を実施。
イプソスは日本のクレジットカードの利用実態を明らかにするべく185,000人にオンラインアンケートを実施し、その結果を公表しました。(中略)
調査概要
- 調査時期:2016年11月8日~11月18日
- 調査対象者:日本全国18~79歳の男女
- サンプルサイズ:185,495名 うち151,565名が過去6ヶ月にクレジットカードの利用ありと回答
- 調査方法:オンライン調査
この統計データが面白いな…と思うのは、クレジットカードの保有枚数ではなく利用枚数に関するデータである点。
- 通常の統計:保有している枚数を調べる
- 今回の統計:利用した枚数を調べる
18歳から79歳の185,495名を対象にオンライン調査を実施したところ、81%に当たる151,565名が過去6ヶ月以内にクレジットカードを1枚以上利用したと回答した。
利用したクレジットカードは延べ300,538枚で、一人平均1.99枚(人口構成によるウェイト修正後)を利用している。
つまりクレジットカードを持っているけれども、過去6ヶ月の間に1度も使わなかった…という「持っているだけのユーザー(非アクティブユーザー)」を弾いた結果になっているので、かなり実態に近いところが探れた統計結果になっているのではないでしょうか?
過去6ヶ月にカードを利用した比率:
…となると気になるのは、過去6ヶ月の間にクレジットカードを利用した方の比率になるのですが、どうやら全体の81%に当たる方が利用していた模様。
- 185,495名のうち、81%に当たる151,565名が過去6ヶ月以内にクレジットカードを1枚以上利用した
一般的にクレジットカードの保有率は90%弱と言われるため、この利用率は異常に高い気がしなくもありませんが、たぶんこれは今回の統計が「オンライン調査」だからでしょう。
要するにネットでアンケートに回答できるような層は、クレジットカード保有率も高く利用にも積極的な可能性が高いってこと。
ひっくり返せばデジタルに無縁な方ほど現金主義者が多いこと側面もありそうな気がします。
20代の利用率は低い:
では年代別の利用カード枚数はどうなのか。こちらはやはり年齢が低くなればなるほど利用率の低さが目立つ形になりました。

このあたりはJCBの統計データと合致する部分。
年代が若くなるほどクレジットカード保有率は低い傾向にあるので、その結果、カード利用率が低くなってしまうのも仕方ないところなのかもしれません(今回の統計はクレジットカード保有者に対しての統計ではなく、クレジットカードを持っていない人を含めて実施された統計のため)。
70代の利用率はなんと84%:
あと個人的に意外だったのは70歳~79歳の層でも、クレジットカード利用率が84%と高めに出ていること。
過去6ヶ月の間にクレジットカードを1度も利用しなかった方はわずか16%しかいない&3枚以上のクレジットカードを使い分けている方も1/4程度いることを考えると、もはや高齢だからクレジットカードは敬遠されるとか、クレジットカード会社が高齢者にはカードを発行しない…なんて時代ではないのかもしれませんね。
ただまぁこれも、「オンライン調査に協力できる70代の方の結果」なので、実態はもう少しは低いと想定しておいたほうが良さそうです。
年収別のクレジットカード利用枚数:
次に年収別のクレジットカード利用枚数ですが、下記グラフを見てもらえればわかる通り、年収が低い方であればあるほどカード利用枚数が少なく、年収が高い方であればあるほどカードを利用枚数が多いという結果となりました。
そう、見事なまでに年収とカード利用枚数には相関性があるのですね。
クレジットカード利用者151,565名を年収別で見ると、高年収ほど利用クレジットカード枚数が多い結果となった。
特に5枚以上のクレジットカードを使い分けるヘビーユーザーの比率は年収が高まるほど、高くなる。

もちろん、年収が低い=クレジットカードをたくさん持つことが出来ない…という面があるのはわかりますが、そうはいっても年会費無料のクレジットカードであれば5枚は持てるもの。
年収が低いから1枚しかクレジットカードが持てないわけではありません。
また、今回の統計は「保有枚数」ではなく「利用枚数」なところもミソ。
つまり年収が高い人はクレジットカードを場所によって使い分けている…と言えそうな気がします。
- 年収が低めの方:同じカードを使う傾向に
- 年収が高めの方:複数枚のカードを使い分ける
無駄に多くのクレジットカードを保有しているわけではないようです。
年収別のクレジットカードグレード:
もうひとつ参考までに、年収別のクレジットカードグレードについて。
こちらはやはり、年収が高い方であればあるほどゴールドカードやプラチナカード保有率が高い傾向にあるようです。
下記のグラフでは、利用しているすべてのクレジットカードのグレードを年収別に集計した。
年収が高いほど、ゴールドカード、プラチナカードの利用率が高まり、年収が2,000万円を超える層では40%以上がゴールドまたはプラチナカードを利用している。

反面、面白いなと思うのは年収200万円未満の方でもゴールドカード保有率が8%ある点。
今やそのくらい、ゴールドカードが多くの方にとって身近な存在になったとも言えそうです(ゴールドカードの審査基準は下記記事参照)。
キャッシュレス社会化を歓迎するかどうか:
博報堂生活総合研究所が2017年12月15日付けで公表した統計データによると、将来、紙幣や硬貨などの現金を使う必要のない「キャッシュレス社会」になったほうがいいと思っている20~69歳の男女は、全体の48.6%という割合になったようです(引用はこちら)。
Q.近い将来、紙幣や硬貨などの現金を使う必要がない「キャッシュレス社会」になるのではないかといわれています。
あなたご自身のお気持ちは「キャッシュレス社会」に「なった方がよい」「ならない方がよい」のどちらに近いですか?(単一回答)

ご覧のように全体的な世論としてはやや反対派が多いキャッシュレス社会化ですが、実は男性はどちらかというとキャッシュレス社会に賛成なのに対し、女性はやや強めにキャッシュレス化に対して反対している統計結果に。
つまり女性の反対派が多かったため、全体の割合としてキャッシュレス社会に反対な割合が多くなったようです。
- 男性:賛成が58.7%、反対が41.3%
- 女性:賛成が38.5%、反対が61.5%
男女で意見は正反対(男性は賛成、女性は反対が多数)
性別でみると、男女で意見は正反対。男性は賛成派(58.7%)、女性は反対派(61.5%)が多数となっています。
年齢があがるにつれキャッシュレス社会に賛成:
年代別の統計データについては下記表の通り。
男女ともに年齢があがるにつれてキャッシュレス社会への賛同割合が増えるというのは面白いですね。

どうやら年齢があがると「お釣り等を気にせずに支払いが出来る点」にメリットを感じる方が多いために、キャッシュレス化を歓迎する統計結果が出やすい傾向にあるようです。
世の中のイメージとはちょっと逆ですよね(印象としては若い人ほどキャッシュレス社会に賛同し、高齢になるほど反対するイメージがある)。
キャッシュレス化に賛成の声は?:
参考までにキャッシュレス化に賛成している方の理由にはどのようなものがあるのでしょうか?こちらもいくつか抜粋して紹介させてもらいます。
現金を持たなくてよいから
- 現金を持ちたくない。不潔だし、財布も重くなる(女性53歳・東京都)
- 現金の出し入れで次の方を待たせる場合も多いので、持ち歩かない方が便利(女性63歳・茨城県)
利便性が高いから
- 口座から現金をおろしたり、送金に手間がかかるより、利便性が上がりそう(男性54歳・東京都)
- キャッシュレスは便利。でも、お金を手にしないのは少し淋しい気もする(女性54歳・青森県)
やりとりがスムーズだから
- 通販もクレジットカードがあれば、振込や代引の手間もなくなる(女性30歳・愛知県)
- レジの待ちの時間が減りそう(男性64歳・熊本県)
管理しやすいから
- いつ何にお金を使ったかが、インターネットやアプリで管理できれば楽だから(男性39歳・宮城県)
- 使用履歴が電子化され、閲覧や見直しができる(女性51歳・大阪府)
個人的に「ポイントが貯まりやすいから」とか、「お得だから」という理由が上位に来るのかな…なんて思っていたんですが、統計データを見る限りではそれ以外にメリットを感じている方が多そうな感じ。
なかでも「現金を持たなくてよいから」と「利便性が高いから」について賛同をしているキャッシュレス社会推進派の方が多い状況でした(下記表はその比率)。

キャッシュレス化に反対の声は?
反対にキャッシュレス化に反対している方の声にはどのようなものがあるのか…についても引用させてもらいます(こちらは公平性を保つために全部、引用)。
浪費しそうだから
- 使った感覚がない売買は湯水の如く金を使いそうで怖い(女性35歳・埼玉県)
- 支払いの実感がなくなると、ためらいなく借金や浪費をする人が増えそう(男性26歳・京都府)
お金の感覚が麻痺しそうだから
- 考えなしに買ってしまいそう。現金は減るのを実感でき、考えて買い物ができる(女性60歳・静岡県)
- いくら使ったかがわかりづらい。支払い可能限度から逸脱する可能性がある(男性34歳・東京都)
お金のありがたみがなくなりそうだから
- お金を稼ぐありがたみがわからなくなりそう(女性36歳・宮城県)
- お金の価値が軽いものに変わってきてしまいそう(男性37歳・香川県)
現金は必要だから
- システムがダウンして混乱を招く事態になった時、やはり現金はあった方がよい(女性52歳・東京都)
- 電脳世界の通貨は何らかの障害や天災が発生した際、使い物にならない(男性42歳・大阪府)
犯罪が多発しそうだから
- 暗証番号や個人情報が流出して、犯罪が起きる可能性がある(男性27歳・東京都)
- システムの脆弱性などで不正が行われる心配もある(女性66歳・東京都)
やはり上位2つには「浪費しそう」と「お金の感覚が麻痺しそう」が選ばれましたが、どちらもお金を使いすぎてしまいそうだからキャッシュレス社会は嫌…そんな意識が強いのかなという気がします。
また、災害時の対応や、個人情報漏洩などのセキュリティ面の不安も根強いみたいですね。
個人的には火災によって燃えてしまったり、落としてしまえば戻ってくることのない現金よりも、クレジットカードや電子マネーのほうが安心かなと思えるのですが、この辺は人それぞれ感じ方が違うのでしょう(回答の比率については下記表を参照)。

時代は徐々にキャッシュレス社会に:
ここまでキャッシュレス社会に関する賛否を紹介させていただきましたが、間違いなく言えるのは、この先、そのスピードが早いか遅いかはわかりませんが、世の中は徐々にキャッシュレス社会になっていくこと。
実際、下記の質問への回答が、その「流れ」を顕著にあらわしている気がします。
Q.次の支払い方法が占める割合は、最近2~3年で増えていますか、減っていますか。それぞれの支払い方法ごとにあてはまるものをお選びください。(各.単一回答)

さてさて、どうなることやらですが、個人的には日本経済にもっと元気になっていってほしいので、1日でも早いキャッシュレス社会実現に期待したいなぁ…と思う日々です(どうしてキャッシュレス化すると経済が元気になるのかについては下記記事を参照)。
20代男女の現金払い比率:
2017年に20歳~29歳の男女1,000人を対象に統計をとった「20代の金銭感覚についての意識調査2017」。
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社は、2017年10月2日~5日の4日間、20歳~29歳の男女を対象に「20代の金銭感覚についての意識調査2017」をインターネットリサーチで実施し、1,000名の有効サンプルの集計結果を公開しました。(調査協力会社:ネットエイジア株式会社)
このの中にあったクレジットカードに関連する統計データが面白かったので、今の20代がお金についてどのような意識を持っているのか知りたい方はご覧ください。
支払い金額に対する支払い手段について:
まず、クレジットカード情報サイトを運営している人間として一番気になった統計結果がこちら(以下の金額の買い物で選ぶ支払い方法は?)。
- オレンジ色:現金払い
- 水色:電子マネー払い
- 濃い青色:クレジットカード払い
- 黄色:デビットカード払い

ご覧いただければわかる通り、100円や500円といった支払い方法ではだいたい7割の方が現金払いを利用しているものの、1,000円、5,000円、1万円と支払い金額が増えていくごとにクレジットカードの割合が高まっていくことがわかります。
100円~5,000円の買い物では「現金」が多数派(100円76.8%、500円69.1%、1,000円66.0%、5,000円54.2%)になり、1万円以上は「キャッシュレス」が多数派(1万円52.7%、3万円65.3%、5万円69.9%、10万円73.0%)になりました。
1万円以上の買い物ではクレジットカードなどのキャッシュレス払いを使う人が多いことから、普段の財布の中身は1万円以下の人が多いのかもしれません。
とはいえ、1万円以上の支払いであっても現金払いを利用する方は全体の約半数とかなりの数。
更に10万円以上の支払いでも4人に1人の方が現金を選んでいるのは、やはり現金払いに対する安心感とカード払いに対する不信感などがあるのでしょう。
携帯に電子マネーアプリを入れる20代は違う結果:
この統計結果に対して、今度は携帯の中に電子マネーアプリ(おサイフケータイ含む)を入れている人に、金額ごとの決済手段を質問した統計結果がこちら。

どうでしょうか?
だいぶ現金決済の比率が下がり、電子マネーを利用する比率が高い状況がありますね。100円や500円の支払いでは約40%近くの場合で電子マネーを支払いに使っていることがわかります。
加えて若干…ではありますが、携帯の中に電子マネーアプリを入れている人は、1万円や3万円といった高額の支払いをする際にはクレジットカードを使う傾向にもあるようです。
- 10万円支払い時(全体):クレジットカード比率は66.7%
- 10万円支払い時(電子マネーアプリ利用者):カード比率は75.3%
いわゆるキャッシュレス派のわかものはしっかりクレジットカード払いを使っている、そんな感じですね。
若者でもおサイフケータイはあまり使わない:
ちなみに、携帯の中に電子マネーアプリを入れている人というのは20代でも全体の17%程度しかいないもんなんですね。
個人的には20代であれば新しい決済手段に対する抵抗感がなくて、もう少し多くの方がおサイフケータイ機能を活用しているもんだと思っていましたが、現実はそうでもない模様。
支払いに使えるアプリでは、スマホをかざすだけで支払いできる「電子マネーアプリ」が17.0%、中国で利用者が爆発的に増えていることで最近注目を集めている「QRコード決済アプリ」が5.8%となりました。
まぁおサイフケータイに対応したAndroid端末保有者が少ないとか、iPhoneはiPhoneでも旧型のiPhoneを利用しているなどなど、カードタイプの電子マネーを使わなくちゃいけない理由もきっとあるのでしょう。
事実、電子マネーそのものを利用している方は全体の75%と決して少なくない数字となりました(とはいえ、そのほとんどが電車やバス移動用のSuicaやPASMOなどの交通系ICカードであると想定)。

全回答者(1,000名)に、普段使いしている電子マネーは何種類あるか聞いたところ、「1種類」が33.0%、「2種類」が25.0%、「3種類以上」が16.9%となり、それらを合計した『電子マネーを普段使いしている』割合は7割半(74.9%)となりました。20代の4人に3人は、電子マネーを普段使いしているようです。
電子マネー利用には男女比もある:
あと、1,000人程度への統計なので偏りがあるかもしれませんが、携帯電話の中に電子マネーアプリを利用している比率については男女の偏りがあります。
- 20代の男性:利用率は22.8%
- 20代の女性:利用率は11.2%
男女別にみると、男性は「電子マネーアプリ」が22.8%で、女性(11.2%)のおよそ2倍の割合となりました。
その辺を探っていくと、なぜ20代の若者がクレジットカードや電子マネーを支払いで使わないのかという理由が見えてくるのかもしれません。
Tポイントの年代別&男女別アクティブ会員数:
Tカードを現在進行中で利用している方は6,408万人。
そんな途方もない統計データを、Tカードの発行&管理を行っているCCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)が公式リリースにて発表しました。
-
CCC カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(当該データは削除済)
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO:増田宗昭、「以下CCC」)が提供するTカードにおいて、直近1年間にTカードを利用いただいているアクティブな会員、かつTカードを複数枚お持ちの方は1人として重複を除いたユニークな会員である「アクティブ・ユニーク」な年間利用会員数が、日本総人口の50%を突破いたしました。
こう書くと、『いやいや、Tカードを使っている人がそんないるはずないし、どうせ1人で何枚も持ってる人の分を数えてるだけなんだろ?』なんて思うTカード非保有者の方は多いかもですが、この数字は直近1年間にTカードを利用したアクティブ会員数&複数枚保有者を1人として数えた数字とのこと。
つまり仮にこの数字が正しければ…という前提は付きますが、CCC側が発表している通り、「日本人の2人に1人がTカードを利用している」のは大げさな表現ではないように思います。

月に1度でも使う人は4,738万人:
しかもTカードを月に1度でも使う方の数は4,738万人…と、こちらもかなり大きな数字に。要するにTポイントを率先して貯めている方は非常に多いということが出来るので、猫も杓子もTポイントが大好きといった状況です。
- 2017年8月の月間アクティブ会員数:4,738万人
- 2017年8月の平均週間アクティブ会員数:2,976万人
Tカードの月間利用会員数(アクティブ・ユニーク)は2017年8月末時点で4,738万人と過去最高の稼働数となり、日本総人口に占める割合では37.3%となりました。
また、週間利用会員数(アクティブ・ユニーク)は、2017年8月の平均で2,976万人、日本総人口に占める割合は23.4%となり、月間とあわせて週間の会員数も過去最高となりました。
20代の保有率はハンパない:
更に20代のみで絞っていうと、Tカードの保有&利用率はハンパない状況。
なんと82.4%もの方がTポイントを貯めていることになるので、Tポイント非保有者の比率はわずか17.6%しかありません。
- Tポイントを貯めている20代:82.4%
- Tポイントを貯めていない20代:17.6%
日本総人口の各年代に占める会員数の割合は、20代が82.4%(前年同月比101.7%)、30代が75.0%(前年同月比102.6%)、40代が74.0%(前年同月比107.2%)、50代が65.6%(前値同月比109.2%)、60代が47.8%(前年同月比112.7%)、70代が32.9%(前年同月比121.0%)となり、20~50代では半数以上、また60代においても半数近くの人がTカードをご利用いただくまでに成長いたしました。
また、60代や70代におけるTカード利用率も地味に凄くて、60代で47.8%、70代で32.9%というのは驚異的。
もはやTポイントカード=国民的ポイントカードといえるのかもしれません(Tポイントを貯めたい方は下記記事を参考に)。
コンビニで現金払いをする理由について:
マイナビニュースが自社ニュース購読者885人に向けて取った、『コンビニで買い物をする際、どの支払い方法をすることが最も多いですか?』というアンケート結果が非常に面白かったので引用させていただきます(引用元はこちら)。
コンビニで買い物をする際、現金以外にも、クレジットやデビットカード、電子マネーなど様々な支払い方法を選ぶことができるが、あなたはどれで支払うことが多いだろうか。マイナビニュース会員885名に聞いてみた。
気になるアンケート結果は下記の通り。
Q.コンビニで買い物をする際、どの支払い方法をすることが最も多いですか?
- 1位 現金 37.9%
- 2位 電子マネー 29.8%
- 3位 クレジット・デビットカード 29.4%
- 4位 その他(自由回答) 2.9%
現金払い派が37.9%と、電子マネー派、クレジットカード派を大きく上回る結果になりました。
まぁこのアンケート結果は調査人数が885人と少ないこと、そしてどの層を対象に取られたアンケートなのかかが全くわからないものなので、結果については大きな偏りがある可能性大。
とはいえ、まだまだ電子マネー派、クレジットカード派は少数派なのですね。
現金払いをする理由が面白い:
ではなぜコンビニで現金払いを利用するのか?今回のマイナビニュースのアンケート調査では、そのあたりにもしっかり踏み込んでいたので紹介させていただきます。
まずは『クレジットカードや電子マネーだと利用金額が把握しにくい』というもの。
- 「どれだけお金を使ったか、把握できなくなるから」(56歳男性/教育/専門サービス関連)
- 「いくら使ったのか分からなくなる(現金以外は使った実感が全くない)」(49歳男性/フードビジネス/販売・サービス関連)
- 「カードをメインにすると、今自由に使える現金がいくらあるのか分からなくなりそうだから」(40歳男性/化粧品・医薬品/専門職関連)
これについて私は昔、まったくその考え方を理解できなかったのですが、どうやら現金払い派の方は財布の中に残っている残高で、「今月、あといくら使える」といった現状把握をしているようです。
なるほど、たしかに財布を見れば利用可能残高がわかるという意味では、理にかなった使い方だなと思いますが、だったら銀行口座を1つにまとめてデビットカード払いをしたほうが残高管理はわかりやすいのになぁ…とは思いますね(デビットカードについてはこちらの記事を参照)。
- 財布で残高を管理:毎回、数えないといけない
- デビットカード&銀行口座で残高を管理:アプリ等で残高確認が可能
加えて財布の中にその月の生活費を全部入れておくのもちょっと怖い。うっかり財布を紛失してしまったら、それで生活費がゼロになるのは恐怖です。
現金のほうが無駄遣いを防げる:
次に現金払いのほうが無駄遣いを防げると思ってる方も多い模様。
これは昔から言われていることですし、実際、クレジットカードを持つと際限なく買い物をしてしまう方もいるので、この考え方は理解できます。
- 「カード払いにすると、使いすぎてしまうことがあるから」(32歳男性/海運・鉄道・空輸・陸運/事務・企画・経営関連)
- 「手元に現金が残るため、ついつい予算オーバーしがちだから」(44歳男性/食品/営業関連)
- 「現金の方が使用した実感があるため無駄遣いを防げるから」(38歳男性/建設・土木/建築・土木関連技術職)
まぁそれだったらこれも銀行口座残高以上に支払いで使えないデビットカードで解決可能なので、やり方次第。
また、クレジットカードを使うにしても、利用限度額を低めに設定してキャッシング枠を0円にするなどすれば無駄遣いを防げるので、興味がある方は無駄遣いを防ぐこちらの記事もあわせてお読みいただければなと思います。
現金払いのほうが早い:
ここまで紹介した2つの理由は、たしかに一理あるなぁと思うものなんですが、ここから先で紹介する現金払いを使う理由についてはやや理解に苦しむものばかり。
最初は『クレジットカードよりも現金払いのほうが支払いがスムーズだから』というものです。
- 「コンビニくらいでは現金の方が早い」(49歳男性/サービス/メカトロ関連技術職)
- 「現金の方が早いから」(53歳男性/その他/その他・専業主婦等)
- 「コンビニでは早く支払いをして出たい」(58歳男性/その他/事務・企画・経営関連)
この点はもう、一度、騙されたと思ってクレジットカード払いを使ってみて…と言うしか他にない感じ。
事実、コンビニでのクレジットカード払いというのはとんでもなく早いので、現金払いより遅いということはまずありえません。

さすがにタバコや新聞を1つだけ購入する時のような指名買い&レジに並んでいる時に現金を用意しておくような場合にはさすがに勝てませんが、それ以外なら99%、カード払いのほうに分があるので是非とも試してみてください。
一度味わってしまうと、もう二度と現金払いには戻れません。
少額決済で使うのは気が引ける:
次は『コンビニでは数百円程度の買い物しかしないのに、そこでクレジットカード払いを使うのは悪い』という理由です。
- 「少ない金額で使うのは抵抗がある」(46歳男性/海運・鉄道・空輸・陸運/技能工・運輸・設備関連)
- 「コンビニでは少額の支払いがほとんどなのでクレジットカードを使うのは気が引ける。3,000円以上じゃないとクレジットカードを使わないようにしている」(44歳男性/鉱業・金属製品・鉄鋼/技能工・運輸・設備関連)
- 「コンビニの買い物はたまにしかしないし、金額も500円くらいなので、クレジットカードを使うのに抵抗があるから」(36歳女性/インターネット関連/クリエイティブ関連)
確かに少し前の感覚でいうと、クレジットカードは3,000円以上の支払いで使うもんだ…という常識があったのも事実ですが、最近では電子マネーの登場もあってか、クレジットカード利用は少額でもOKになりつつあります。
また、コンビニで働いている店員さんとしても、現金の受け渡しでミスが生じやすい現金払いは大変なもの。
細かい釣り銭を用意したり、1万円札のお釣りを数えるのは苦労するものなので、少額決済でもクレジットカードを使ってあげたほうがラクになる意見もありますよ。
財布の中の小銭を減らしたい:
コンビニで現金払いを使う理由、最後は『財布の中の小銭を減らしたいから』というもの。
- 「小銭を消化したいから」(26歳女性/官公庁/事務・企画・経営関連)
- 「少額なので余っている小銭を減らしたい」(53歳女性/その他/その他・専業主婦等)
- 「細かいお金を減らしたいから」(39歳男性/食品/技能工・運輸・設備関連)
私も稀に、財布の中の小銭が増えた時に確かに現金払いをしますけれども、常に…ではないので、この理由で現金払いをしている人がいたら「?」ですね。
それに普段から現金払いを使っていなければ小銭が財布の中に貯まることもないので、まさに本末転倒なことでもあるのかなと。
- 普段から現金払い:釣り銭が溜まりやすい
- 普段から電子決済:釣り銭が溜まりにくい
代わりにクレジットカードや電子マネーを使えば小銭で悩むこともなくなります。
有名な方々も否定的な意見:
ここまでコンビニで現金払いをする理由について紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
この件についてはネット界隈の重鎮である下記の方々も否定的なコメントを出していますが、私自身は別に理由あって現金払いを使っているなら構わないとは思います。
総じて現金派はアタマが悪いという結論しかないです。このアンケート見る限り。。
— 堀江貴文(Takafumi Horie) (@takapon_jp) 2017年8月18日
コンビニの支払い、4割が現金派 – 電子マネーやクレカを使わない理由は? (マイナビニュース) - https://t.co/jbSfwkCmlQ
失礼ですがバカでいらっしゃいますか? >「利用金額が把握しづらい」「無駄遣いを防ぐため」 〜コンビニの支払い、4割が現金派 - 電子マネーやクレカを使わない理由は? 〜https://t.co/BZfsM45MN1
— 田端 信太郎 (@tabbata) 2017年8月18日
しかし、「クレジットカード払い=遅い」とか、「クレジットカード払い=少額だと迷惑」などの間違った知識を元に現金払いをしているなら、是非とも、この機会にクレジットカードや電子マネー決済に切り替えてほしいですね。
そのほうが日本経済全体が活性化するので、巡り巡って自分へのリターンも期待できますよ(よくある勘違いについては下記記事参照)。
ファミマのキャッシュレス決済比率:
2017年現在、大手コンビニのひとつであるファミリーマートではどのくらいクレジットカードや電子マネー決済が使われているかのデータです。
ファミマの社長である高柳氏が朝日新聞のインタビューにて回答しました。(朝日新聞より引用 ※記事削除済み)。
高柳社長は「金融技術に強い専門家が少なく、伊藤忠の力を借りたい」と説明。ファミマでは、まだお客の9割弱が現金で「電子マネー化を進められれば、お釣りのやりとりなど店側の負担も減らせる」と述べた。
この90%近くが現金払いである…という数字って、みなさんは驚愕の数字であると思いませんか?
なにせファミマではVisaやJCBといったクレジットカードはもちろん、Suica、楽天Edy、iD、QUICPay、WAONが使える状況にも関わらず、これらの支払い方法を使う利用者は全体の10%程度しかいないってこと。
- 現金払いのお客さん:90%弱
- カード、電子マネー払い:10%ちょっと
いくら日本人が現金払い好きだといっても、ポイント面でのメリットが乏しい現金払いにここまで固執するのかと驚くばかりです。
ローソンのキャッシュレス決済比率:
2017年現在の、大手コンビニ「ローソン」におけるキャッシュレス決済比率です(SankeiBizより引用)。
ローソンバンク設立準備会社について。現状ではセブン銀行に空港も押さえられている。これからやっていくといっても、勝ち目がないんじゃないか
竹増貞信社長「(中略)店舗では現金のお客さまが75%を超えている。これが今後どうなるか。後発なりのメリットを取り込んで、利便性のあるサービスを提供できるようにし、持たざるところには、圧倒的な差別を図っていきたい」
記事中にある数字を書き出すとこんな感じ。
- 現金払いの比率:75%以上
- キャッシュレス決済比率:25%以下
これだけクレジットカード決済やSuicaや楽天Edyといった電子マネーが普及している中で、未だに大手コンビニでの決済比率は現金に大きく偏重しているのかと思うと、日本がキャッシュレス社会になるための道のりは険しいものになりそうですね。
なにせVisaカード、Mastercard、JCBカード、アメックスなどのクレジットカードから、楽天Edy、Suica、WAON、iD、QUICPayなどの電子マネー、そしてLINE PAYカードやJCBプレモカードにクオカード等を合算しても全体の1/4に届いていないことに。
キャッシュレス社会化への道のりは非常に険しいなと思わされます。
カード決済比率は低いけれども:
ちなみに2015年時点での個人消費に占めるクレジットカード決済比率は16%で、電子マネーを加えても22%弱しかないので、情報通な方に言わせればコンビニで75%の人が現金払いを使ってるといわれてもおかしくないと思われるかもしれません(下記統計はこちらから引用)。

しかし、これらの数字は『現金払いのみしか使うことが出来ないお店』での支払いを含む比率であり、且つPay-easyや銀行振込等を除いた場合の電子決済比率は30%を越えるので、ここまで主要コンビニでクレジットカードや電子マネーが使われていないことは驚きと言えそうです。
2016年の統計データ:

2016年に集計された統計データやアンケート調査です。
働く女性が貯めてるポイント制度ランキング:
20~39歳の働く女性が所有&利用しているポイントサービスがわかる統計データです(こちらより引用)。
モバイルリサーチを展開するネットエイジア株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:三清 慎一郎、以下ネットエイジア)は、2015年12月21日~25日の5日間、ポイント活用に関する調査をインターネットリサーチにより実施し、20歳~39歳のビジネスウーマン(アルバイト・パートを除く女性有職者)2,000名の回答を集計いたしました。
利用率第1位はTポイントカード:
ネットエイジアの統計によると、働く女性が利用しているポイントサービス第1位はやはりTポイントの模様。実に70.9%もの方がTポイントサービスを貯めているという結果になりました。
まぁたぶんですがTポイントサービス利用者=Tポイントカード保有者だと思うので、この数字はすごいですよね。
いかに多くの方が財布の中にTポイントカードを入れているかがわかります(ファミマ等でTポイントカードはお持ちですか?と聞いても良い比率)。
20歳~39歳のビジネスウーマン(アルバイト・パートを除く女性有職者)2,000名が利用しているポイントサービスの確認を行った。利用しているポイントサービスを複数回答形式で聞いたところ、「Tポイント」が最も高く70.9%となった。前回調査(2015年2月発表)に引き続き、2年連続で1位となっている。
次いで「Ponta」が62.8%、「楽天スーパーポイント」が49.2%となり、<共通ポイント系・オンライン通販系>のポイントサービスがトップ3となった。
ランキング第2位はポンタ:
第2位はPonta。
こちらの利用率も62.8%とかなり立派な数字なんですが、合併(?)予定のリクルートポイントの利用率と合算すると66.4%になるのでTポイントサービス利用者に肉薄しそうな感じです。
- Tポイントサービス:70.4%
- ポンタ+リクルートポイント:66.4%
ただ正直、最近ではポンタの勢いに陰りが見えてきている感もあるので、なんらかのテコ入れでもしない限りはTポイントサービスには追いつかないことでしょう。
第3位は楽天スーパーポイント:
第3位は楽天スーパーポイントの49.2%。
個人的には楽天市場の利用者ってもっと比率が高いと思っていたんですが、意外にも少ない数字になりました。ざっくり働く女性の半分程度が楽天市場を利用&楽天ポイントを貯めていることになります。
ちなみに楽天と競合するAmazonポイントの利用率も下記のように低い状況。
そのため、今回の統計はもしかすると働く若い女性が「意識的に貯めているかどうか」で、利用しているポイントサービスにチェックを入れた結果なのかもしれません。
- Amazonポイント:25.1%
- リクルートポイント:16.6%
Tポイントカードやポンタカードは日々、持ち歩くことが多いので、貯めている意識も高いのでしょう。
WAONポイントやnanacoポイントも健闘:
その他の順位としては下記の引用画像の通り。

WAONポイントやnanacoポイントを貯めている人は30%強と、所有率としてはかなり健闘しているような気がします。
反面、保有者も利用者も多いSuicaのポイント制度であるSuicaポイントの利用率はわずか18.0%と、多くの方がポイント制度があること自体を知らない結果となってしまったようです。
4位、5位には<電子マネー系※1>の「WAONポイント」(32.7%)、「nanacoポイント」(30.8%)が入り、「交通系ICカードのポイント(Suicaポイントなど)」(18.0%)は8位となった。
7位には<携帯キャリア系>の「au WALLETポイントプログラム」(19.9%)が入り、「dポイントクラブ(旧・ドコモプレミアクラブ)」(17.1%)が10位となった。
<家電量販店系>では「ヤマダポイント(ヤマダ電機)」(17.2%)が9位となり、家電量販店系で唯一トップテンにランクインした。
※Suicaポイントは現在、JRE POINTに統合されています。詳しくは下記記事を参考に。
Amazonと楽天市場はどちらが人気なのか:
MMD研究所というところが2016年5月24日付で調査した「2016年ネットショッピングに関する調査」において、過去6ヶ月以内に利用したネットショッピングサイトを調べた統計がありました。
MMDLabo株式会社は、同社が運営するMMD研究所と株式会社コロプラが提供するスマートフォン向けインターネットリサーチサービス「スマートアンサー」にて共同調査を行い、第13弾として「2016年ネットショッピングに関する調査」を実施致しました。
ちょっと興味深い数値になっているので、ネット通販を普段から利用している方は是非、ご覧ください。
楽天市場がAmazonに完敗:
気になる統計結果は下記の通り。
ご覧いただけるように、Amazonが楽天市場の利用者を大きく離し、ダントツの1位になっています。

- Amazon:76.9%
- 楽天:48.3%
- ヤフーショッピング:18.7%
- ブランド等のネットショップ:10.5%
- ヨドバシ.com:9.5%
- ネットスーパー:4.7%
- その他:16.1%
注目すべきはやはり楽天利用者の少なさ。
しかも今回の統計は「スマートフォンを所有する15~49歳の男女」に対して行われたものなので、どちらかというと通販利用に対して積極的な層への調査になるのですが、それでも半数に届かない結果とはかなり残念な数字かもしれません。
反面、Amazon利用者については全体の3/4以上と、もはやネット通販を利用する方のほぼ全員がAmazonを利用しているといっても過言ではない状況。
Amazon vs 楽天市場は、Amazonの完勝なのは間違いないでしょう。
PC利用者を含めればここまで差はつかない:
ではなぜ楽天がこれほどまでにAmazonに完敗してしまったのかについては、調査対象がスマートフォンを所有する層であることが考えられます。
実際、下記画像は「6ヶ月以内にスマートフォンで購入した商品」はどれかについて調べた質問ですが、10代と20代が『本・雑誌・コミック』を選択。
このあたりのジャンルはAmazonが楽天を大きくリードしている分野なので、結果的にAmazon利用者数が伸びた可能性があります。
最近6カ月以内にスマートフォンで購入した商品を聞いたところ、10代は「本・雑誌・コミック、CD・DVD・ブルーレイ、衣服・靴・アクセサリー」、20代は「本・雑誌・コミック、衣服・靴・アクセサリー、生活雑貨・日用品」、30代は「生活雑貨・日用品、衣服・靴・アクセサリー、本・雑誌・コミック」、40代は「生活雑貨・日用品、衣服・靴・アクセサリー、食料品」の順となり年代別で購入した商品が異なる結果となった。

そのため、たぶんパソコン利用者を含めて統計を取った場合には、楽天とAmazonの差はここまで開かなったかもしれません。
スマホで買い物をする時代に:
加えてもうひとつ。
楽天 vs Amazonという構図以外にも、この「2016年ネットショッピングに関する調査」には面白い統計結果もあったのでそれを紹介しておきます。
ネットショッピングをする時に最も使うデバイスを聞いたところ、「スマートフォン」が65.8%で最多となり、前年と比較すると5.5ポイント増の結果となった。

そもそもこの統計自体が「スマホを持っている人への調査」なので、ややスマートフォン寄りの統計結果になっている可能性は高いですが、それでも大部分の人がスマホ経由で買い物をするのが普通な時代になりつつある感じ。
こうやって常識というものは徐々に、変わっていくのかもしれません。
積極的にクレカを使いたくない人は6割:
クレジットカードを積極的に使いたいかどうか。
内閣府が2016年9月1日に公表した「クレジットカード取引の安心・安全に関する世論調査(PDF)」によると、約6割の回答者が『積極的に使いたくない』と回答したようです。
あなたは,クレジットカードを積極的に利用したいと思いますか。
- そう思う 20.3%
- どちらかといえばそう思う 19.5%
- どちらかといえばそう思わない 24.0%
- そう思わない 33.8%
- わからない 2.4%
反面、クレジットカードを積極的に利用したいかどうかの設問に対し、「そう思う」や「どちらかといえばそう思う」と回答した方は全体の約4割。
- 約4割の人:積極的に利用したい
- 約6割の人:あまり利用したくはない
質問の仕方にもよるのかもしれませんが、少なくともこの統計結果では『クレジットカードをあまり使いたくない』と考えている方のほうが多数派であることがわかります。
クレジットカードを使いたくない理由:
では、クレジットカード利用に消極的な方はなぜ、クレジットカードを使いたくないのでしょうか?このあたりについてもこの統計では調査されていました。
あなたがクレジットカードを積極的に利用したいと思わない理由は何ですか。この中からいくつでもあげてください。
- 日々の生活においてクレジットカードがなくても不便を感じないから 55.4%
- クレジットカードの紛失・盗難により,第三者に使用されるおそれがあるから 41.3%
- 個人情報などがクレジットカード会社や利用した店舗などから漏えいし,不正利用されてしまう懸念があるから 35.4%
- 予算以上の買い物をしてしまうから 33.7%
- 月々の利用金額が分からなくなってしまうから 27.3%
正直、今回の統計調査では回答可能な項目がこれら5つに加えて「その他」しか用意されていなかっため、比率が高めに出ている可能性はありますが、それでも多くの方がクレジットカードを使いたくない理由として、『不正利用』や『不要さ』をあげていることがわかります。
特に一番回答が多かった「日常の生活においてクレジットカードがなくても不便を感じないから」は、クレジットカードそのものの否定ですね(苦笑)
日本では下記、NILSON REPORTの統計結果のように、現金払いがまだまだ根強いんだなと再確認させられます(こちらより転載)。

まだまだ世論は『クレジットカード=怖いもの』なのでしょう。さらなる啓蒙活動が必要と思われます。
現金払いを好むのは男性よりも女性:
大手広告代理店の博報堂が2016年9月30日(金)~10月5日(水) にインターネット経由で3,097人に対して「お金に関する生活者意識調査」を実施。
博報堂金融マーケティングプロジェクトは、FinTechによる金融分野でのテクノロジー進化が、生活者に対して、どのような意識変化、行動変化をもたらすのかを分析するために、「決済」と「スマートフォン」を軸とした「お金」に関する生活者意識調査を実施しました。
その中で注目してほしいのは下記設問の回答です。
Q.下記について 1 ヶ月あたりの使用金額を、合計を 100%とした場合の各割合をお知らせください。
※利用されていないものについては「0」とご記入ください。

ちょっと小さいのでスマートフォンからは見難いかもしれませんが、全体の51.4%の決済が未だに現金払いという結果に。
- 現金:51.4%
- デビットカード:1.6%
- クレジットカード:21.6%
- 電子マネーICカード:9.1%
- インターネットバンキング:5.3%
- カードでのインターネット決済:8.5%
- その他:2.6%
とりわけ10代、20代の現金決済比率は高く、男性よりも女性のほうが現金払いを好んで使っている状況も浮き彫りになりました。
個人的には「女性の方がカード決済が好き(依存気味)」という印象を持っていただけに、この結果はちょっと意外でしたね。
調査結果によると、1ヶ月あたりの使用金額の決済手段別比率は、依然「現金」決済が51.4%と半数以上を占めるものの、「クレジットカード」21.6%、「ICカード」9.1%、「カードでのインターネット決済」8.5%、「デビットカード」1.6%で、「カード決済」の合計も40.8%と4割程度を占めることがわかりました。
現金払いは年代があがるほど減る傾向:
また、現金払いの比率は年代があがるほど減少傾向になり、反対にクレジットカード決済比率が高まる結果にもなっています。
- 若い世代:現金払いが多く、カード払いや電子マネー払いは少ない
- 50代~60代:現金払いが少なく、カード払いは電子マネー払いが多い
これ、なんとなく若い世代ほど電子マネーやクレジットカードを活用し、年代があがるほどに昔ながらの方が増えて現金払い比率が高いのかな…なんて固定観念を持っている方は私を含めて未だに多いとは思いますが、現実はもはや、そんな感じではないのかもしれませんね。
電子決済の普及が日本のGDPに与える影響:
クレジットカードや電子マネーといったキャッシュレス決済が普及すると日本のGDPにどのくらい影響があるのか、その点について国際ブランドのVisaが発表した統計データです(引用元はこちら)。
2016年3月9日、米国カリフォルニア州サンフランシスコ – Visa Inc.(以下Visa)は本日、世界70ヶ国の経済成長における電子決済の影響を分析した2016年度調査の結果を発表しました。(中略)
この調査では、2011年から2015年までの期間、対象の70ヶ国においてクレジットカード、デビットカード、プリペイドカードなどの電子決済商品の利用が拡大した結果、GDPが2,960億ドル(約33兆4,480億円1)増加し、商品やサービスの家計消費が年平均で0.18パーセント上昇したことが示されました。また、調査対象の5年間における電子決済の利用増により、年平均で260万もの新規雇用が創出されたと推計しています。(中略)
日本に関してみてみると、電子決済利用の拡大は、2011~2015年期の日本経済に対して、107.4億ドル(約1兆2,136億円)増という効果をもたらし、年平均27,840件相当の雇用も新たに生み出しています。
まぁあくまでこの統計結果はクレジットカードの国際ブランドであるVisa Inc.によるものなので、ある程度は中身が電子決済よりになっている点は否めません。
しかしそれでもこれだけのGDP増加への効果があることを考えると、あながち馬鹿には出来ない統計だと私は思います。
では、どうしてクレジットカードやデビットカードといった支払いが増えるとGDPを押し上げる効果があるのか?Visa Inc.によると主に4つほど理由があるとのことなので、わかりやすくそれぞれ簡単に説明していきます。
1.現金処理費用の減少:
現金を取り扱うというのは小銭の用意、釣り銭間違え、保管コストなどなど、見えないコストがかかると言われています。
たとえば学生時代にスーパーマーケットのレジ打ちのバイトをして、レジ内の現金がずれて困った経験をお持ちの方はきっと多いはず。
他にも1円玉や100円玉がなくなって事務所まで小銭交換しにいったとか、1,000円札が足りなくなって銀行まで走ったとか、そういう作業が現金処理の見えないコストです。
反面、クレジットカードや電子マネー払いであれば小銭の用意も不要ですし、残高がずれる心配はありません。
- 現金払い:釣り銭の用意や、残高管理が大変
- カード払い:釣り銭不要&残高管理も不要
確かに加盟店手数料はかかりますが、現金処理が不要になるメリットは大きいと言われています。
2.加盟店に対する支払い保証:
次はクレジットカードやデビットカード払いには、加盟店に対する支払い保証がある点。
たとえば銀行振込で携帯料金を払っている方が支払い遅延を起こした場合、そのお金を回収する責任はソフトバンクやNTTドコモといった企業が担当することになりますが、クレジットカード払いで携帯料金を払っている場合にはカード会社からお金を回収することが出来ます。
- 銀行振替の場合:お金の回収をするのが面倒(自分で回収)
- カード払いの場合:カード会社が責任をもって入金してくれる
つまり、いくらクレジットカード保有者が金欠になってしまったとしても、支払いを踏み倒そうとしたとしても、クレジットカード払いが成立さえしてしまえばお店は100%、そのお金を回収可能。
もちろん電子決済であれば自分でお客さんのところまでいって「金払え!」というやりとりをする必要性もないので、そういう手間やコストを抑えることができる点がGDPを押し上げているのではないか。
そんな理屈です。
3.政府の潜在的税収増に繋がる:
3つ目はクレジットカード決済をするとお金の流れが明確になるので、お店側が脱税をしにくくなる点があげられます。
みなさんもたぶん、個人経営の飲食店で見たことがあるとは思いますが、電卓を叩くだけでレジを全く打たない飲食店ってありますよね。
ああいうお店のすべてで脱税をしているとはいいませんが、現金払いは履歴が残らない分、お店はカンタンに売上をごまかせてしまうもの。
その点、クレジットカードや電子マネーといった電子決済だと支払い履歴がデータとしてしっかり残るので、店舗側も売上を誤魔化すことができないのです。
- 現金払い:売上をごまかしやすい
- カード払い:銀行入金なのでごまかしにくい
結果としてクレジットカード払いが普及すれば小売店の納税額が増え、政府の税収が増える構図がある…というのがVisaの考え。
そして政府の税収が増えれば、その分、社会保障などにお金をまわせるためにGDPがあがることとなります。
4.消費者における金融サービスへの参加促進:
最後はこれ、私たち消費者がクレジットカードや電子マネーを持てば金融知識が豊富になっていき、投資活動などの金融サービスへの参加が促進されていくのではないか?というものですね。
これについては明確な統計等があるわけではないでしょうけれども、私自身もクレジットカードを好きになったことで金融知識が一気に増えた人間なのでその効果は間違いなくあると思います。
世の中のお金の流れがわかるようになるメリットは計り知れません。お金に詳しくなれる書籍は下記記事を参考にどうぞ。
中国人観光客が日本で使ったクレジットカードについて:
日本にやってきた中国人観光客が、コンビニでの支払いに使ったクレジットカードは「銀聯カード」。そんな統計データをUnionPay International(銀聯国際)が2016年2月3日付けで発表しました。
コンビニエンスストアでクレジットカードを利用した人の94.8%がUnionPay(銀聯)カードを利用したと回答しています。UnionPay International(銀聯国際)では訪日中国人客の日本でのクレジットカード 利用実態について、「訪日中国人観光客のクレジットカード利用実態調査」を実施いたしました。
訪日中国人観光客300名を対象としたこの調査では、約9割の訪日中国人観光客が旅行中にクレジットカードを利用しており、そのうち半数近くが現金よりクレジットカードをメインに使用していることがわかりました。(中略)
コンビニでのカード利用者の94.8%以上が、昨年10月よりコンビニエンスストアで利用可能となったUnionPay(銀聯)カードを利用していることもわかりました。
銀聯カードの利用率がすごい:
今回の統計データはあくまで銀聯いわく…といった数字にはなりますが、それにしてもすごい比率ですよね、これ。
- 銀聯カード:94.8%
- その他のカード:5.2%
もうほとんどの中国人観光客が、コンビニで銀聯カードを利用したのと同じくらいの数字。
VisaカードやMasterCardを利用している人は全体の5.2%しかいないので、無視してもいいんじゃないかと思えるほどです。
中国人観光客による売上アップを目指すなら:
つまり今後、繁華街にお店を構える店舗経営者の方が中国人観光客による売上を伸ばそうと思っているのであれば、銀聯カード決済導入が不可欠。
少しでもはやく銀聯カード決済を導入し、店舗入口にUnionPayのロゴを貼りだすようにすれば、きっとそれだけで中国人観光客の来店が増加&売上も増えると思われます。
- 銀聯カード対応なし:中国人観光客が入ってこない
- 銀聯カード対応あり:中国人観光客の利用が増える
そのくらい、中国人の銀聯カード利用率は高いですよ(銀聯カード決済導入の相談はこちら)。
女性よりも男性のほうがクレカ嫌いが多い:
マイナビウーマンのアンケート調査にて、女性よりも男性のほうがクレジットカード嫌いが多いのかも?なんて統計結果がありました。
『マイナビウーマン』にて2016年8月にWebアンケート。有効回答数400件(22歳~39歳の働く男女)
気になるその調査結果は下記の通り(7位以下は割愛)。
Q.1カ月間のクレジットカードの平均的な利用額はいくらですか?
【女性】
- 第1位 1万~2万円未満……13.1%
- 第2位 10万円以上……12.1%
- 第3位 0~5,000円未満……10.15%
- 同率3位 2万~3万円未満……10.15%
- 同率3位 3万~4万円未満……10.15%
- 第6位 4万~5万円未満……9.7%
【男性】
- 第1位 10万円以上……18.8%
- 第2位 2万~3万円未満……15.3%
- 第3位 利用しない……10.85%
- 第4位 0~5,000円未満……9.9%
- 第5位 4万~5万円未満……7.4%
- 第6位 1万~2万円未満……6.9%
ご覧いただいたように女性は僅差で月間1~2万円使う方が多いようなんですが、男性は10万円以上利用している方がダントツの1位。
これだけを見ると「男性はクレジットカードを積極的に使う人が多い」といった結論にもなりそうなのですが、注目すべきは男性の3位の欄ですね。
「クレジットカードを利用しない」と回答した方も同様に多い結果となりました(クレジットカードを持っているけれども使っていない方は0~5,000円未満の項目にチェックを付けるはずなので、この「利用しない」は、クレジットカードを1枚も持っていないことを意味する)。
男性はクレジットカードの好き嫌いが顕著:
まぁこの統計結果は働く男女400人へのアンケート結果なので統計データとしてはやや不十分なところもあるのですが、傾向として『男性はクレジットカードの好き嫌いが顕著である』と言えそうな感じ。
確かに私の身の回りでもクレジットカードを絶対に使いたくない男性がいる反面、日々、コツコツといつでもどこでもカード払いしている人も多いなど、両極端な気がするので、意外とズレてない調査結果なのかもと思います。
- 男性:カードが嫌いな人も多ければ、好きな人も多い傾向
- 女性:カードが嫌いな人は少ないが、好きな人も少ない傾向
反面、女性はみんなクレジットカードを持ってるけど、そこまで積極的にカードを使いこなしていないのかもしれません。
Tポイントカードのアクティブ会員数:
2016年9月末現在、Tカードを直近1年以内に利用したアクティブ会員数は6,000万人。
そんな驚きの数字をTカードを管理&発行しているカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が発表しました。
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO:増田宗昭、「以下CCC」)が提供するTカードにおいて、直近1年間にTカードを利用いただいているアクティブな会員、かつTカードを複数枚お持ちの方は1人として重複を除いたユニークな会員である「アクティブ・ユニーク」なT会員数が、2016年9月末で6000万人になります。
これは、日本の2人に1人がTカードを利用している数字となります。
あくまでこの6,000万人という数字は、CCC側が発表している数値のためどこまで正確な数値なのかはわかりませんが、仮に正しいとするとものすごい数字ですよね、これ。

なぜなら現在、日本の人口は約1億2,700万人なので、なんと日本人の2人に1人がTポイントカードを普段から利用している計算。
更に高齢の方やポイントカードを持ち歩かない子供世代を除くと、3人に2人くらいがTポイントを貯めてる計算になっちゃうんじゃないんでしょうか?(CCCによると動労人口の実に80%がT会員だそうです)。
恐るべし、Tポイントです。
日本総人口の1億2708万人に占めるT会員の割合は約5割、また15歳から64歳までの7636万人のうちT会員が占める割合は約8割におよびます。
※Tポイントをもっと効率よく貯めたい方は、下記記事もあわせてご覧ください。
2015年の統計データ:

2015年に集計された統計データやアンケート調査です。
働く女性の支持率No.1カードについて:
マイナビウーマンが2015年1月に実施したアンケート調査です(引用元はこちら)。
『マイナビウーマン』にて2015年1月にWebアンケート。有効回答数231件(22歳~34歳の働く女性)。
このアンケート調査において、22歳から34歳の働く女性に支持されているクレジットカードランキングが発表されました。
気になる結果は下記の通りとなります。
Q.あなたが普段使ってるクレジットカードの種類を教えてください。
- 1位 楽天カード……25.3%
- 2位 エポスカード……12.7%
- 3位 セゾンカード……10.2%
(中略)『マイナビウーマン』にて2015年1月にWebアンケート。有効回答数231件(22歳~34歳の働く女性)
楽天カード利用者が圧倒的に多い:
このアンケート結果では22歳から34歳の働く女性の4分の1が、楽天カードをメインカードとして使っていることが判明。
2位にエポスカード、3位にセゾンカードがランクインしていますが、それらのカードと比べても楽天カードの利用率がダントツ飛び抜けていることがわかります。
いやはや、これほどまでに差がつくとは、楽天カードの人気はすごいですね。中でも若年層による人気がハンパない感じです。
楽天カードの魅力はポイント:
尚、今回のアンケート調査によると、多くの女性が楽天カードを魅力的に感じているのは節約面での保有メリットをあげているようです。
確かに大多数のクレジットカードが1,000円利用で1ポイント(5円分)しか貯まらない中、楽天カードの場合には100円単位で1円分のポイントもらえるのは大きなメリット。
- 「ポイントがつく! 光熱費などの支払いでポイントを貯め、それで楽天でお買い物」(27歳/その他/販売職・サービス系)
- 「100円で1ポイント貯まるし、貯まったポイントは楽天市場で現金同様に使えるため」(27歳/商社・卸/事務系専門職)
細かい部分まできっちりとポイント獲得できる&1ポイント単位で利用できる点は、節約に対して敏感な女性にとって嬉しい制度なのではないでしょうか?(ポイントが貯まりやすいカードと貯まりにくいカードの差は下記図解を参照)

ポイント還元率の高さが他のカードとくらべて光ります(楽天カードのデメリットは下記記事参照)。
WAONの年間利用額と総発行枚数:
イオン系の電子マネーである「WAON(ワオン)」の年間利用額がついに2兆円を突破したようです。イオン株式会社がプレスリリースにて発表しました。
「WAON」は2007年4月に誕生して以来、スピーディーな決済、煩雑な小銭管理が不要となる利便性、WAONポイントが貯められるお得さや、利用できる加盟店が全国24万5,000箇所まで拡大したことなどが高く評価され、2015年度の利用金額は、同年の市場規模の4割※を超える約2兆592億円にまで成長しました。
この2兆円という数字は、イオン側によると国内シェア4割にあたる数字とのこと(野村総合研究所「IT ナビゲーター2016 年版」スマートペイメント市場データをもとづく試算)。

ただこの数字はあくまで「イオンによる試算」なので、実際にはもう少しシェアが少ない可能性は高いと思われます。
事実、ライバルのnanacoやSuica利用者も多いですし、楽天Edyだってまだまだ利用者が多いので、実数としては33%くらいかなと個人的には予測。
それでも十分に凄いシェア率です。
累計発行枚数は5,610万枚:
尚、電子マネーWAONの累計発行枚数は5,610万枚とのこと。

こちらもあくまで累計の発行枚数で、現在、実際に使われているWAONの枚数ではありませんが、少なくとも2,000万人くらいの方は日々、WAONを買い物で使っている感じだと思われます。
「G.G WAON」「JMB WAON」「サッカー大好きWAON」など、お客さまのご利用目的にあわせた様々な種類のカードを発行しており、累計発行枚数は5,610万枚となりました。(2016年2月末現在)
まぁほんと、イオンモールにいくとそこら中で「ワオンっ!」という決済音が鳴り響いていることを考えると、イオンを日常的に使う方にとっては一番身近で使いやすい電子マネーなのでしょう。
そして20代や30代だけでなく、60代以上の年配の方にまでWAONは人気なので、イオンは電子マネーを上手に浸透させたなぁとも思います。
外国人観光客は日本のキャッシュレス事情に不満:
株式会社日本政策投資銀行が公益財団法人日本交通公社というところで組んで訪日外国人観光客にアンケート調査を行ったところ、約70%の方が日本にもっとクレジットカードやキャッシュカードが使える場所が多ければ買い物をもっとしたのに…と回答したようです。
こちらの記事よりデータを引用&転載させてもらいます。
日本で外貨両替やクレジットカード・キャッシュカードを利用できる場所が、もし今より多かったら?(回答は1つ)

統計概要は下記の通り。
株式会社日本政策投資銀行(代表取締役社長:柳 正憲、以下「DBJ」という。)は、公益財団法人日本交通公社(会長:志賀 典人、以下「JTBF」という。)と共同で、「DBJ・JTBF アジア8地域・訪日外国人旅行者の意向調査(平成27年版)」と題した調査レポートを発行しました。
DBJでは、平成24年より継続的にアジア8地域(韓国、中国、台湾、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア)の旅行嗜好や訪日経験の有無によるニーズの変化を把握することを目的に、海外旅行経験者を対象としたインターネットによるアンケート調査を実施していますが、本年はJTBFと共同で、7月に4回目となる調査を実施しました。
カード払いを導入しないと機会損失に:
この件については当サイト『クレジットカードの読みもの』でも度々、外国人観光客経由の売上を増やしたいならクレジットカード払いを導入して店頭にロゴステッカーを貼ったほうがいいよ…ということを書いてきましたが、今回の統計データを見る限りでも、その対策は間違っていなかったことが判明。
なにせ「おそらくもっと多くのお金を使ったと思う」と「もっと多くのお金を使ったと思う」と回答した方の比率は実に70%にもなるわけですからね。
これは逆に言えば30%弱の訪日外国人しか自分が買いたいものが買えたと思っていないことになるので、日本の店舗経営者の方はかなりの機会損失を起こしていることになります。
- 30%弱の訪日外国人:買いたいものが買えた
- 70%の訪日外国人:買いたいものが買えなかった可能性大
経営者ならこの勿体なさがわかるはずです。
外国人観光客が買い物をした場所の統計も:
ついでに面白い統計データだなと思ったので、中国人観光客や台湾人観光客といった、外国人観光客が買い物をした場所の統計データも転載(クリックすると拡大します)。

香港やシンガポールからの外国人観光客が百貨店での買い物を好む反面、インドネシアや中国、韓国からの観光客はあんまり百貨店での買い物が好きではないみたいですね。
他、台湾人観光客はドラッグストアを、香港人観光客はスーパーマーケットでの買い物を好むことがわかります(国民性の違いというよりかは、ガイドブック等での紹介のされ方の違いかもしれません)。
2014年の統計データ:

2014年に集計された統計データやアンケート調査です。
国際ブランド別の国内利用率:
iPhoneやiPadといったタブレット端末を利用して、クレジットカード決済を提供しているCoineyが実施した統計データです(30代から60代の男女500人にクレジットカードに対して行われた、利用状況の調査結果)。
スマートフォンやタブレット端末を使ったクレジットカード決済サービス「Coiney(コイニー)」を展開しているコイニー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:佐俣奈緒子、以下コイニー)は、30代から60代の男女500人にクレジットカードに関する利用状況の調査を実施しました。
Visaカード利用者がほとんど:
この統計結果によると、75%ものクレジットカード利用者がVisaカードを利用していることが判明(下記画像を参照)。
いくら複数選択できる重複回答OKな統計データとはいえ、このVisaカード利用率は異常に高いですよね。

反面、Visaカードのライバルとも言えるMasterCardは30%程度のみ。
Visaの尋常じゃない強さの前には霞んでしまいそうですが、MasterCardも日本国内ではだいぶシェアがあるのがわかります。
JCBカードは厳しい:
そして日本の国際ブランドであるJCBですが、こちらの利用率はついに半数以下。47.6%という厳しい数字になってしまっています。
- Visa利用率:75%
- JCB利用率:47.6%
日本でクレジットカードで使っている人たちの中でJCBカードが、半分のシェアすら獲得できていないかと思うと、個人的にかなり残念に思いますね。
このままでは国際ブランドの中でのJCBの存在感が薄れていく一方なので、もっと頑張って欲しいです(国際ブランドの詳細は下記記事を参照)。
中国における銀聯カード発行枚数:
2014年2月現在の、中国国内で発行されているクレジットカード&デビットカード発行枚数の統計データです(引用元はこちら)。
- デビットカード:44億8,100万枚(前年同期比17.2%増)、平均保有枚数3.64枚
- クレジットカード:4億5,500万枚(前年同期比16.5%増)、平均保有枚数0.34枚
2014年12月末時点で、中国において発行されている銀行カードの総量は、49億3600万枚に達した。
発行枚数の内訳は、デビットカードが、2013年同期比17.2%増の44億8100万枚を占める。クレジットカードは、2013年末から16.5%増加し、4億5500万枚となった。
これを見て、『中国ではクレジットカードなどの電子決済が普及していないのか』なんて思ってしまうところですが、中国国内で流通しているのはデビットカードが中心。
実にクレジットカードの10倍ものデビットカードが流通しているので、クレジットカードの枚数だけを見て『中国は遅れている』と思ってはいけないのです。
中国のデビットカードは銀聯カード:
ちなみに中国におけるデビットカードのほとんどが、銀聯カードと呼ばれる国際ブランドが付いたデビットカードです。
最近では日本にも中国人観光客が増えたせいか、UnionPayと書かれた下記のようなマークを店頭で見たことがある方も多いはず(UnionPay=中国銀聯)。

特に浅草や銀座、京都といった観光地では、所狭しとこのマークが店頭に飾られているので、気になる方は確認してみてくださいね(銀聯カードについて詳しくは下記記事参照)。
利用明細書を確認しない人の比率:
年収が500~800万円程度あるのに貯金が100万円以下しかない30代男性200人に訪ねたアンケート結果に、クレジットカードの明細書を定期的に確認しない人の比率が紹介されていました。
年収500万円~800万円で「貯金100万円以下」という30代男性200人(未既婚各100人)を対象にインターネットでアンケートを実施
(中略)
- カード明細は見ない 59%
特定の属性を持った30代男性がアンケート対象という括りはありますが、そのうち59%もの方がクレジットカード明細書を定期的に確認していない事実は驚愕そのもの。
なにせ半分以上もの人が、明細書のチェックをしていないことになるわけですからね。まさにみなさんズボラとしか言いようがありません。
クレジットカード明細を確認しない怖さ:
当然、クレジットカードの利用明細書を定期的に確認しないってことは、クレジットカードを誰かに不正利用されたとしても気付くわけなし。

これが数千円程度の不正利用であればちょっとの後悔で済みますけど、10万円単位の不正利用に気付かなかった場合には泣くに泣けない状態になるだけ。
更に100万円以上の不正利用…なんてことになれば、利用明細のチェックを怠ったことで人生すら狂いかねないのでご注意ください。
下手すると自己破産コースへまっしぐらです(クレジットカードを不正利用された際の補償は下記記事参照)。
クレジットカードへの不満点&不安点:
ジャパンネット銀行がクレジットカードを使う上での不満や不安に関する統計調査を実施(こちらの統計データ)。
株式会社ジャパンネット銀行(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:小村充広、以下ジャパンネット銀行)は、2014年2月28日(金曜日)~2014年3月3日(月曜日)、ショッピングの支払いに関するアンケート調査を実施しました。
本アンケートでは、ネットショッピング利用経験のある全国の18歳から69歳の男女600名にご協力いただきました。
この統計結果によると、クレジットカード利用者がクレジットカードについて強く不満&不安に思っていること第1位は意外や意外、『年会費がかかること』だそうです。
- 第1位:年会費がかかる
- 第2位:情報漏洩などセキュリティの問題
- 第3位:お店によって使えないところがある
- 第4位:サインなど支払い手続きの煩雑さ
- 第5位:購買履歴が記録される
- 第6位:支払いが後回しになる
次いでセキュリティ面での不安、お店によって使えないところがある…に続く流れ。

多くの方がクレジットカードの年会費やセキュリティ対策に不満を感じていることがわかりました(年会費負担がイヤなら下記記事で紹介中の年会費無料クレジットカードを作ればいいだけなんですけどね)。
2012年の統計データ:

2012年に集計された統計データやアンケート調査です。
クレジットカードを初めて作った年齢:
クレジットカードを初めて作った時期に関する統計データが楽天リサーチにありました(楽天リサーチの統計)。
楽天リサーチ株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:森 学、以下 「楽天リサーチ」)と楽天カード株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:穂坂 雅之、以下 「楽天カード」)は、クレジットカードに関するインターネット調査を実施しました。
今回の調査は、2月28日から29日の2日間、楽天リサーチ登録モニター(約220万人)の中から、全国の18歳から69歳の男女計1,200人を対象に行いました。
初めてクレジットカードを作った年齢をまとめた統計データは下記の通り。
- 18才~20才:25.9%
- 21才~22才:18.6%
- 23才~25才:21.7%
- 26才~30才:12.9%
- 31才~40才:11.7%
- 41才~50才:5.0%
- 51才以上:4.2%
統計データを分析してみると、だいたい30才頃までに80%という大多数の方が1枚目のクレジットカードを作成していることがわかります。
20歳までに4人に1人が作ってる:
特に18才~20才という当時の未成年を含む年代で25.9%、つまり1/4以上の方が作っているのは大きいですね。
昨今、大学や専門学校入学と同時に学生証としてクレジットカードを作らされるケースが増えているので、その影響もあるのでしょうが、多くの方が成人を待たずにクレジットカードを作っているのは興味深いです。
10代からカードを持つのが普通になってきているとも言えそうです。
新社会人になる25才までには70%弱が作成:
また、25才までの区切りでみてもて、70%弱の方がはじめてのクレジットカード作成をしていることが判明。
逆に言えば25才以降ではじめてクレジットカードを作った方は、わずか30%ちょっとしかいないのですね。
- 25歳までにカードを作る人:全体の70%
- 25歳以降ではじめてカードを作る人:30%ちょっと
やはり社会人になったら1枚くらいはクレジットカードを持ちたいと思う、『クレジットカード=大人』といった印象を持っている方が多い背景があると私は予測。
なにせタバコやお酒と並んで、クレジットカードは大人だからこそ持つことを許可されている支払い道具ですからね。小さい頃から保有を夢見ていた方も多いはずです。
40才以降ではじめてカードを作る方も10%:
ここまで紹介させていただいたいように、30歳までに80%程度の方が作ってしまうクレジットカードですが、40代以降になってはじめてクレジットカードを作った方も10%ほど存在。
正直、その年齢になるまで作ったことがなかった方は一体どのような考え方をしていたのかはわかりませんが、クレジットカード=怖い、現金払い=正しいといった考えが、今も根強く残っていることも影響しているのかもしれません。
この辺りからも、まだまだ日本は現金社会であることがわかります(これからはじめてクレジットカードを作ろうとかと悩んでいる方は、是非、初めてのカード作成についての情報をまとめた下記記事もどうぞ)。
他の統計データまとめ:

クレジットカード保有枚数等のデータは別記事にまとめてあるので、もっと多くの統計データを見たい方はそれらの記事もあわせてご覧ください。
クレジットカードの国内発行枚数について:
現在、日本国内ではどのくらいのクレジットカード枚数が発行されているのかをまとめた記事です。
あわせて男女別や年代別のクレジットカード保有率など、属性を絞った上での保有率も紹介していますよ。
電子マネーの発行枚数について:
Suica、WAON、楽天Edy、nanacoなどなど、国内の主要な電子マネー発行枚数をまとめた記事です。
最新の発行枚数を知りたい方、電子マネーごとのシェア率を知りたい方は参考にどうぞ。Kitacaやはやかけんなど、地方で流通している交通系ICカードの発行枚数もまとめています。
統計データを見つけ次第、まとめます:

ここまで多数の統計データを紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
このページは過去ログ用の倉庫としてこういったデータを見つけ次第、蓄積させていこうと思うので、統計やアンケート結果に興味がある方は定期的に覗きに来てもらえると嬉しいです。
いやいや、自分は最新情報を追いかけたいと思われる方は、当サイトのTwitterアカウントフォローをどうぞ。
以上、キャッシュレス決済関連の統計データやアンケート調査まとめ!過去に発表されたクレジットカードや電子マネーの統計値が知りたい方に…という話題でした。
参考リンク:
クレジットカードの保有率について詳しく知りたい方は下記記事を参考に。国内全体の発行枚数から、男女別や年代別の保有率までをわかりやすく解説しています。