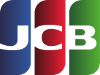時々、『クレジットカードや電子マネーがあるから現金なんて持ち歩かない!なんでもカード払いだぜ!』、そんな私以上のクレジットカード狂信者がいるんですが、これって実はかなり怖い行為なんですよね。
ではなぜ怖いのか?
今回は参考までに、クレジットカードや電子マネーといった電子決済最大の弱点を記事にまとめてみたいと思います。
普段からキャッシュレス決済ばかりで現金を持ち歩いていない方は参考にどうぞ。
電子決済の弱点について:
自然災害発生時にクレジットカードは弱い:
クレジットカードや電子マネーだけでは怖い理由、それは大震災の前でキャッシュレス決済は無力だからです。
一番わかりやすい例でいうと2011年に発生した東日本大震災。
この時はみなさんもご存知の通り、津波や火災によって電気、ガス、水道等のインフラがすべて寸断されてしまいましたが、そういった地域で食料などを手に入れなくてはいけなくなった時にクレジットカードは使えたでしょうか?
まぁ、言うまでもなく無理な話ですよね。
大災害発生時は、現金払いが一番わかりやすい:
その点、1万円札や五千円札といった現金紙幣は、インフラが寸断された時でも支払いに使えるメリット有り。
たとえば惣菜店で100円のパンを買うなら、どんなに強欲な店主がいたとしても1,000円札を握らせれば喜んで売ってくれますが、ゴールドカード片手に『インフラが復旧したら1,000円払うから、パンを1個くれたまえ』では、なにも売ってくれない可能性が高いでしょう(そもそも、クレジットカード払いは電気やネット回線がないと利用できない)。
- 現金払い:災害時でも支払い使える
- カード払い:停電してしまうと使えない
場合によっては惣菜パン1個に1万円払うといっても、クレジットカード払いじゃ交渉が成立しないものと思われます。
電子マネーも災害時は使えない:
同様にSuicaや楽天Edyなどの電子マネーだってそう。
- Suica:災害時は使えない
- 楽天Edy:災害時は使えない
- nanaco:災害時は使えない
- WAON:災害時は使えない
ピッとかシャリーンとか、グイッグベイってするためには電気&通信回線が必要なので、災害時には無力です。
災害が起こることを想定して現金を持つ:
こんな感じで災害はいつ、なんどき起こるか全くわからないもの。
大地震、富士山の噴火、テロ、大停電などなど、インフラが木っ端微塵になってしまうケースはいくらでも存在するので、その時に自分自身はもちろんですが、家族や恋人を守ることが出来るのか。
そういうことを想定し、現金を持ち歩く必要性ってやつを今一度、考えてもらえればな…と思います。
- 現金を持ち歩かない:災害発生時に困る
- 現金を持ち歩く:災害発生時でも多少は安心
万が一の安心感が段違いです。
最悪レベルの災害発生時は現金すらも無効:
それじゃ現金さえあれば災害発生時にも大丈夫か…といえば、実はそうでもありません。過去最悪レベルの災害が発生した場合には、現金すら使えなくなってしまう可能性もありえる話となります。
- 通常の大災害:現金があると安心
- 破滅的な大災害:現金すらも紙切れに
まぁ宇宙人が攻めてきて霞が関や永田町が木っ端微塵に吹き飛んでしまったとか、日本列島が地下空間のガス爆発で沈没してしまったとかでもない限りは大丈夫だとは思いますけど、そういう可能性も考慮しておきたいところ。
現金保有=絶対に安心ではないですよ。
補足:クレジットカードが活躍する例も

ではクレジットカードなんていらないんじゃ?って言われるのもまた違うので、いくつか補足情報を紹介。経営者なら逆転の発想も面白いと思われます。
経営者向け:カード払いOKにすると売上アップ
最近ではキャッシュレス決済が広く浸透してきたせいか、現金をあまり持ち歩かない人が増えてきたのはみなさんもご存知のところ。
そのため、その状況を逆手に取り、災害時でもクレジットカードや電子マネー決済を受け付ける状況を作れれば、大幅な売上アップは確実でしょう。
- 現金払いのみのお店:現金を持ってる人しか使えない
- カード払いOKのお店:現金を持ってない人でも使える
カード払いOKなら、すこし割高に販売してもお客さんが離れることはありません(倫理的にどうなのかといった議論はありそうですけど)。
モバイル決済やQRコード決済なら可能:
ではどうすれば災害時でもキャッシュレス決済を受付可能にできるのか、それは携帯電波を利用したモバイル決済を導入するのがおすすめ。
これなら携帯電波が復旧すればクレジットカード決済や電子マネー決済を受付できるので、携帯の充電に気を使うだけで被災直後の状況を乗り切ることが可能です。
下記画像のようにSuica決済だって携帯電話ひとつで受付できます(詳しくはSquare公式サイト参照)。

PayPayやLINE Payだって受付可能:
他にもここのところ利用者が増えつつあるPayPayやd払いといったQRコード決済も、被災時に受付可能なキャッシュレス決済のひとつ。
こちらはお店独自のQRコード決済を店頭に置いておくだけで支払いを受け付けられるため、停電中だって決済可能となります(PayPay加盟店になる方法はこちら)。

必要なのは携帯電波と、お客さんの携帯充電だけです。
会員サービスが被災時に役立つことはある:
最後にもうひとつ。
大災害の前じゃキャッシュレス決済は無力ですが、クレジットカードを決済サービスではなく、総合的な会員ビジネスと考えるとまた違った見方も可能です。
有名なところだと東日本大震災の発生時、アメリカン・エキスプレス・カードではカード会員全員にひとりひとり電話をかけ、安否確認と何が必要かの連絡を入れたそう。
そしてそれらの要望を元に小学校入学前の子供にランドセルを送ったり、停電中の地域に住んでいる会員にランタンを送るなどのサービスを行ったとのことなので、支払い以外の面でクレジットカードが役に立つことはありますよ。
こういった時は『クレジットカードを持っていて良かったなぁ…』と心底、思えることでしょう。
以上、大災害の前では、クレジットカードは無力!被災時や停電時にキャッシュレス決済は使えないので、どんな場合も多少の現金は必要です…という話題でした。
参考リンク:
そこまでして無理にクレジットカードを普及させなくてもいいんじゃない?そう思える方は下記記事をお読みください。
クレジットカード決済を広める必要性をわかりやすく解説しています。